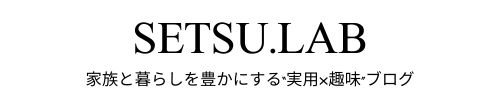ユーザー車検は、自分で陸運局(軽自動車は軽自動車検査協会)に行き、車検を受ける方法です。業者を介さないため費用を抑えられます。
- ユーザー車検に興味はあるが、手続きが面倒そうで不安。
- ディーラーや整備工場に頼むと高額になりがちなので、自分でできる方法を知りたい。
- 「ユーザー車検が安い」と聞いたことがあるが、本当にできるのか不安。
- 整備知識がないけど、自分で車検を通せるのか知りたい。
こんな方のために、やり方(必要書類・手続きの流れ)をまとめました。
ユーザー車検に関する疑問や不安を、全て取り除くことを目標に記事を書きましたので、ぜひ参考にしてください。
※今回は普通車向けのユーザー車検の記事です。
事前準備
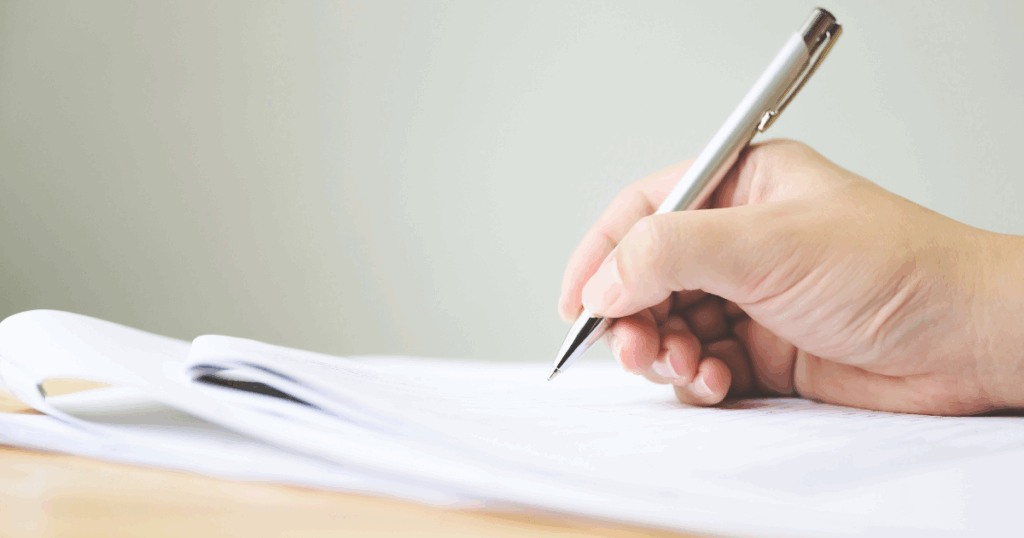
準備する物
- ボールペン
- 鉛筆(シャーペン)
- 消しゴム
- 認印
- クリップボード
- 現金
- 24ヶ月定期点検整備記録簿
- 継続車検申請書 (無くてもOK、詳しくは下記)
- 車検証
- 自賠責保険書
- 自動車納税証明書
車検当日は、上記を全て持参すればOKです。
以下で詳しく解説します。
現金(費用)について

今回、私がユーザー車検をした際の例です。
車種は2020年式のヴォクシーになります。
検査手数料 2,200円
⇒誰でも同じ
自賠責保険料 17,650円
⇒24ヶ月加入なら同じ場合がほとんど
自動車重量税 32,800円
⇒国土交通省のサイトで検索できます
光軸調整代金 3,300円
⇒自分の場合、光軸で不合格になったので、すぐそばのテスター屋さんで調整してもらいました。
※こういったケースも想定して、余分に現金を持って行くようにしましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
合計 55,950円
見ての通り、ディーラー等に車検をお願いするより、かなり費用が抑えられます。
ちなみに、車を購入した販売店での見積もりは12万円でした。
一日で7万円の節約は大きいですよね。
必要書類について

事前に準備する書類
まずは、事前に準備する必要がある書類について解説します。
- 車検証 (車に載っているやつ)
- 自賠責保険証明書(車に載っているやつ)
- 自動車税納税証明書 ※電子決済の場合不要
⇒失くした場合は事前に陸運に電話してみましょう! - 24ヶ月定期点検整備記録簿
上記4つの書類を持参し陸運局へ向かいましょう!
自動車税納税証明書の省略条件
- 自動車税を滞納していない
- 車検が継続車検である
- 納付日から4週間程度経過している ※注
※注 5月~6月中旬にかけて車検を行う場合は自動車納税証明書が必要になる場合があります。
24ヶ月定期点検整備記録簿ちらの書類は、事前に印刷し記入する必要があります。
今回使用させて頂いた、帳票は下記に張り付けてあります。
ダウンロードし、プリントしておいてください。
陸運または自動車協会でもらえる書類
以下の4つは、当日入手が可能な書類です。
赤色のマーカーが引いてある書類は予約をすると、陸運局側で記入箇所を印刷した状態で渡してもらえます。(少々追加記入あり)
- 自賠責保険証明書(新しく契約したもの)
- 継続検査申請書
- 自動車検査票
- 自動車重量税納付書
全て記入することになっても、スムーズに記入できるよう、あらかじめ見本(下書き)をもって行くことをオススメします。
ウォッシャー液の補充
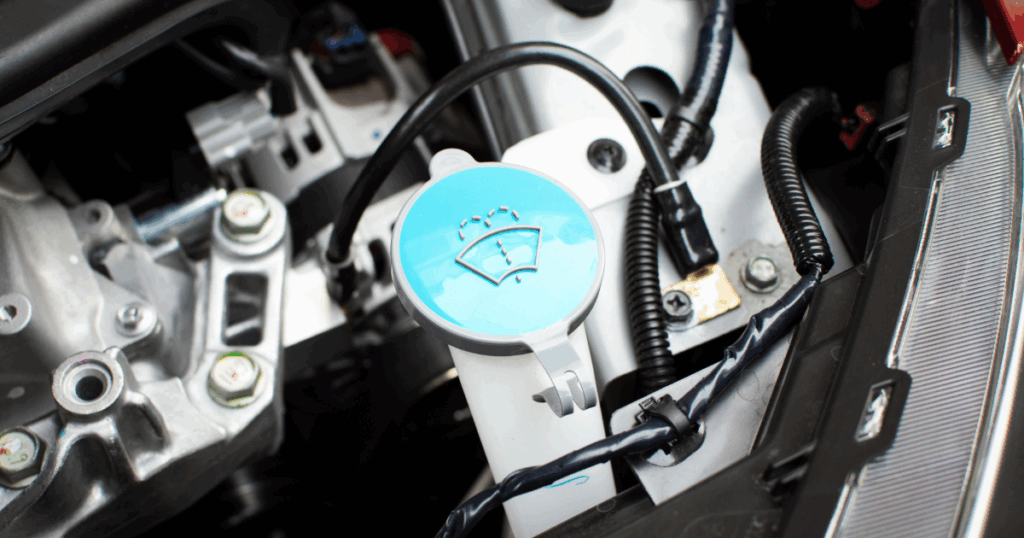
検査時にウォッシャーが正常かどうか確認します。
その際に、ウォッシャーが入っていないと検査に落ちてしまうので水道水でも大丈夫なので忘れずに補充しておきましょう。
車台番号の記載位置の確認

検査時に、検査証に記載されている車と、実際に検査する車が同一かどうか確認します。
その際に、車体のどこかに刻印されている「車台番号」を確認されるのですが、事前に刻印場所を把握しておくと検査時にスムーズになります。
ヴォクシーの場合、運転席のシート下(カーペット下)にありますが、車体によって刻印されている場所が異なります。
最悪、検査員の方と一緒に探しても大丈夫です。笑
点検をする
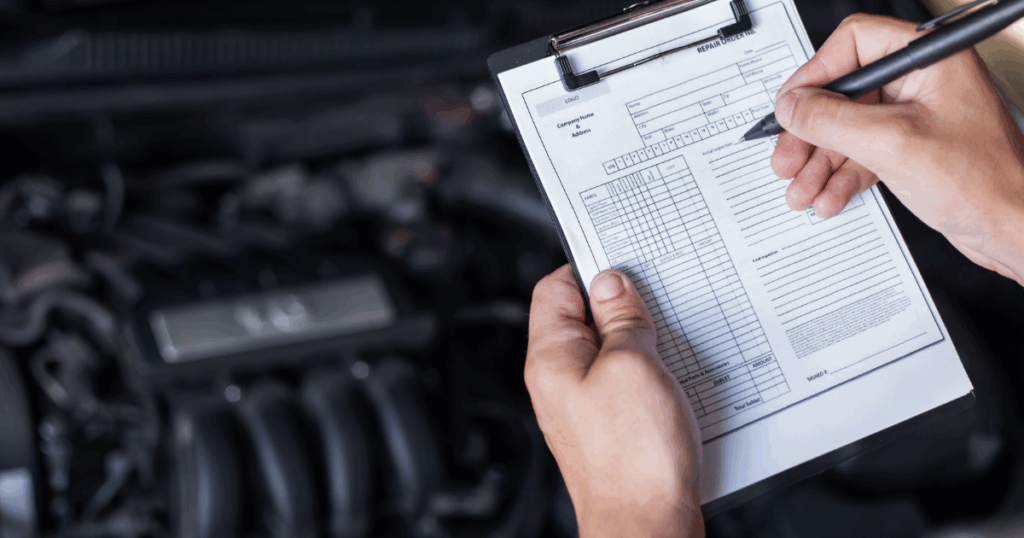
不合格になりやすい、以下の4つは必ず確認しましょう。
- タイヤの溝(1.6mm以上)
- ランプ類の点灯確認
- ワイパー・ウォッシャー液
- オイル漏れ・ブーツ破れ
あとは提出書類の1つ「24か月定期点検記録簿」に沿って点検しましょう。
点検のみ、ディーラー販売店にお任せすることも可能です。
自分で点検する自信がない方は、点検は依頼することをおすすめします。
予約をする
「自動車検査インターネット予約システム」から予約します。
陸運局ごとに空き状況が異なるため、早めに予約するのがベスト
3週間前くらいには予約しておくと安心です。
僕の場合、、、

最寄りの陸運局が空いてない。。
なんてことになりました。
でも大丈夫です。
⇒「継続車検」は日本全国どこでも受けることができます。
上記の事前準備ができれば、完璧です。
自信をもって当日を迎えましょう!
車検当日の流れ
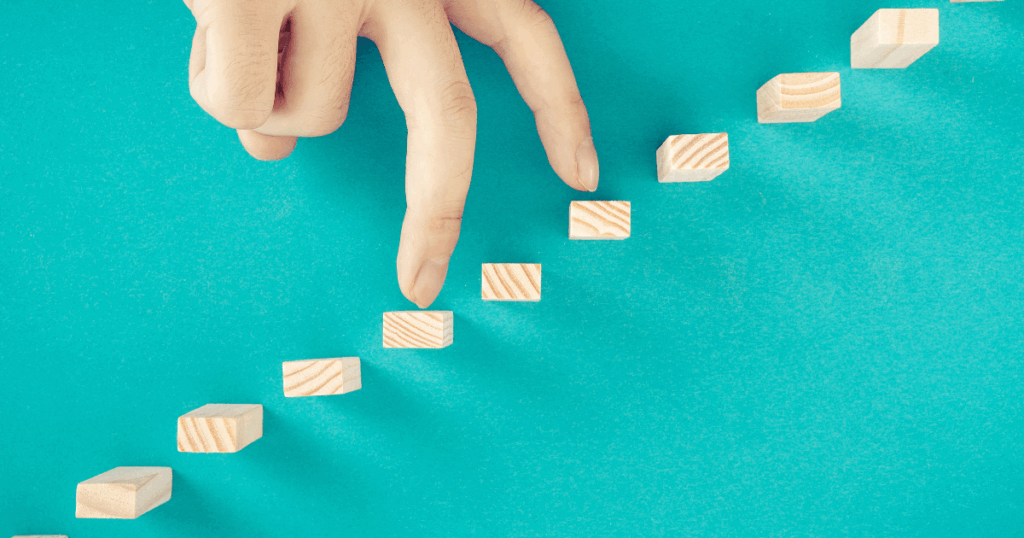
① 受付・書類準備
まず陸運局に到着したら、「受付窓口」で以下の書類を受け取ります。
(事前にインターネット予約している場合は、一部記入済みのこともあります)
- 継続検査申請書
- 自動車検査票
- 自動車重量税納付書
書類を受け取ったら、陸運局の近くにある「自動車協会」へ移動します。
ここで以下の手続きを行います
- 新しい自賠責保険の契約
- 重量税印紙・審査証紙・検査登録印紙の購入(税金・検査費用の支払い)
その後、陸運局に戻って書類一式を提出します。
書類が受理されたら、「呼ばれるのを待つ」→「レーン番号を教えてもらい、検査用の書類を受け取る」という流れになります。
② 検査ラインの下見

検査ラインに並ぶ前に、車検場の見学コースを歩いて、流れや検査項目を事前に確認しておくと安心です。
もし初めてのユーザー車検で不安がある場合は、検査ラインに並ぶ前に「初めてです」と検査官に伝えると、丁寧に教えてくれます。
③ 車両検査(検査ライン)

検査ラインでは、以下の順番で検査を受けます。
- 車両確認(車検証と一致しているかチェック)
※この際に「初めてです」と伝ええる。 - ライト・ワイパー・ホーンの動作確認
- 排ガス検査(プローブをマフラーに挿入)
- ブレーキ・サイドスリップ・スピードメーター検査
- ヘッドライト検査(光軸のズレがあると不合格)
- 下回り検査(リフトで車体を持ち上げ、オイル漏れや損傷の有無を確認)
※基本的には指示に従って操作すればOK!
※焦らず落ち着いて対応することが大切です。
④ 検査後の手続き・車検証の発行

検査が終わったら、再び受付に戻り、書類を提出します。
合格した場合
- 新しい車検証
- 検査標章(ステッカー)
を受け取り、ステッカーをフロントガラスに貼れば完了!
不合格の場合
- 光軸や空気圧など、その場で調整できる項目は当日中に再検査可能
- 修理が必要な場合は「限定自動車検査証」が発行され、後日再検査となります。
まとめ|事前準備がカギ!

- 必要書類の準備
- 車両の検査項目が正常
- 事前予約をする
- 自分でやる気力
この4つがあれば、車検は乗り越えられます!
初めての方も、この記事を参考にすればスムーズに進められるはずです。
しっかり準備して、ユーザー車検にチャレンジしましょう!